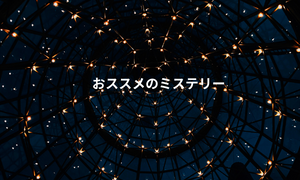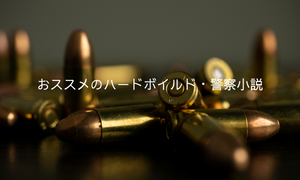最高の教師 1年後 私は生徒に■された。
📁ドラマ 【私の評価】★★★★★(95点)
はじめに
このドラマを見ようと思ったのは、題名に惹かれたからです。
教師ものだとわかりましたが、「最高の」と言うからには、どれだけすごいのだろうかと、懐疑的な気持ちからでした。
きっと、裏切られるに違いない。
そんな私の予想は、逆に裏切られました。
結果としては、見て、大正解でした。
『最高の教師』の感想
衝撃を受けました。
この作品の優れている点は、主に3点あると感じました。
素晴らしい題名
まずは、題名です。
「最高の教師」って、一体どんな教師なんだろうと、興味を惹かれます。
普通は「最高の」といった言葉を題名につけるのは、勇気がいることだと思います。だって、相当ハードルがあがりますからね。にも関わらず、臆することなく題名に使っています。
加えて、「私は生徒に■された」との副題があり、ショッキングで、どんなことが起きたのだろう、その理由はなんだろうかと興味が湧きます。
題名だけで、いろんな想像が掻き立てられました。
予想できない展開
次に、ストーリー展開です。
卒業式の日に、主人公が生徒の誰かから突き落とされて転落するシーンからスタートします。
冒頭から、視聴者の心を鷲掴みにされます。
その後も、視聴者が想像もしていなかった展開が、次から次に起こります。
物語の大枠は、教師もののドラマと同じです。
教師の言葉や行動によって、徐々に生徒が変わっていくというものです。
ですが、個々の生徒が抱えている悩みは、時代をしっかり反映させています。
そして、物語が佳境に差し掛かるにつれて、展開がぐんぐん加速していきます。
特に、前半で物語を推進してきた生徒の死が、視聴者にとっても衝撃的で、後半の展開に物凄いパワーを与えます。
本当によく出来ていて、考え抜かれた展開だと思います。
珠玉の言葉
最後は、言葉です。
この点が、本当に驚きました。
この作品は、ほとんどの時間を、登場人物のセリフで費やしています。
場面は、教室、校舎、主人公の家など、限られた場所で展開され、生徒同士の派手な乱闘シーンなどもほとんどありません。
これだけ、会話のシーンが多いと、普通は飽きます。
にも関わらず、見ていると、毎回、主人公や生徒の語る言葉に釘付けになるのです。
言葉の力とは、これほどまでに強いものなのか。
この作品を見れば、そのことが本当によくわかります。
この作品の脚本家(ツバキマサタカさん)について
この作品は、原作がないため、脚本家が書いたということになります。
脚本家は、ツバキマサタカさんとなっていますが、この人物を検索しても、過去の作品などは出てこず、謎です。
そこで、作品を通じて、この脚本家の人物像を考えてみたいと思います。
新人ではない
これは、かなりの経験がある人でないと、書けないと思います。
この作品にあるのは、斬新さではありません。
世の中を丁寧に見ようとする姿勢です。
個人的な予想ですが、この脚本家は、年齢的に若い人ではなく、年を重ねて世の中を見てきた人ではないかと思います。
作品のテーマが本格的
題名こそショッキングですが、この作品が扱うテーマは、ずっと以前から扱われてきている「いじめ」です。
未だに、いじめはなくなっていませんし、いじめによる死も起きています。
それが起きてしまった時、私達は何度も学校による事なかれ主義の閉鎖的な態度と、遺族の悲痛な訴えを目にします。
ここ数十年、何も変わっていないのです。
この作品は、いじめや、いじめによる死をどう考え、対処していけばよいのかについて、真摯に向き合っています。
この作品の全話を通じたテーマといっても、過言ではないと思います。
そして、このようなテーマを扱おうとする人物は、社会的な問題を正面から捉えて、向き合う本気の覚悟がある人だと思いますし、その覚悟がなければ作れない作品だと思います。
誰が脚本を書いた?
脚本は、ツバキマサタカさんとなっています。
しかし、この人物を検索しても、過去の作品などは出てきません。
新人だから過去作品がない可能性もありますが、先に書いたように、この作品は新人が書いたとは思えないです。
ネットでは、この作品の監督である武藤将吾さんが脚本も書いたのではないかとの説があります。
もしも、ツバキマサタカという人物がいないとしたら、監督が脚本を書いたという説は有力な説だと私も思います。
その説の裏付けとなるかはわかりませんが、個人的には一つのシーンが気になっています。
それは、主人公である教師が突き落とされた時、犯人の顔は見えず、腕しか見えなかったことをもとにして、犯人は無気力で無関心な人間であると結びつけていることです。
この発想は、「絵」を意識している人でないと、出てこない発想ではないかと思うのです。
主人公が犯人の顔を見ていたら、物語の面白さはなくなりますので、何らかの理由をつけて、犯人の顔が見えなかったようにする必要があります。
例えば、犯人は顔を出して主人公を見ていたものの、落ちる時の心理的なショックで、犯人の顔がぼんやりとしか主人公の目に映らなかったとすればいい気がします。
あるいは、2周目の人生を生きるという不思議なことがあるくらいですから、犯人の顔が黒くモヤがかかってわからなかったという、不思議な現象のせいなどにしてもよかったのではないかと思います。
脚本家や小説家のように、物語を書くことを専門にしている方は、そのような手法をとるのではないかと(勝手に)想像します。
ですが、突き落とした腕だけしか映っていないという映像に着眼し、しかもそこから犯人に結びつけていくことができるのは、日頃から「絵」を意識的に撮っている監督という職業ならではの部分が発揮されているのではないかと感じたのです。
断定的なことは言えませんが、ツバキマサタカという人物がいないとしたら、監督が脚本を書いたという説は有力な説だと私も思います。
もう一つ、脚本を書いた人は、突き落とした犯人像にも、こだわりがあるように思えます。
犯人は、映像を取りたいと思っている生徒でした。
周りの状況を冷めた目で客観視していて、無気力、無関心で、周りが白黒に見えると言っています。
周りの状況を冷めた目で客観視するというのは、監督に必須の能力なのかもしれません。
最後に、蛇足ですが、教頭が漢字1文字を書いて、額に入れて飾っていて、卒業式の前日の職員会議では、「刻」という字を書いて見せました。
この漢字一文字で、この作品が言いたかったことが全て表されています。
絵の力が最も出ているシーンだと思いました。
こんな脚本が書けるのも、「絵」が持つ力を十分にわかっている人だからこそではないでしょうか。
教師役について
主人公である教師の九条里奈(松岡茉優)の演技が、とても素晴らしかったです。
女優さんなので、綺麗さがどうしても目立ってしまいがちなものですが、この作品では、九条先生は、終始真剣な表情で、生徒と向き合います。
作品を通じて、九条先生が笑顔になる場面は殆どなかったことも、女優の綺麗さが目立たない効果を生み出して、どこにでもいそうな自然な教師だと感じさせることに成功しています。
もちろん、最も素晴らしいのは、松岡さんの演技力であることは間違いないですね。
珠玉の言葉が、松岡さんの淡々とした、と同時に教師としての覚悟がひしひしと伝わってくる、迫真の演技と合わさって、見ている者の心に響いてきました。
違和感があったこと
完成度が高く、素晴らしい作品であることは間違いありません。
その上で、どんな作品にも、ここはもう少しこうすれば良かったのではと思う点があります。
あくまでも個人的なもので、枝葉の部分です。
ごめんなさい大会
相楽琉偉(さがらるい)が、いじめをしたことについて謝った際、同じく、いじめをしていた仲間達が謝るまではよかったです。
ですが、相楽を犯人だと推測で語った生徒たちも、相楽達に対して謝り始めたシーンでは、ごめんなさいが飛び交うことになりました。
素直さがよいと評価もできますが、安易にごめんなさいが飛び交う印象も与え、少し興ざめでした。
そういうシーンを避けるため、推測で語る生徒を一人にして、その生徒が謝るくらいで十分だったのではないかと思いました。
あなた誰?
失踪した三人組をクラスの皆で探します。
そして、三人組を見つけて、自殺を踏みとどまるための説得のセリフを涙ながらに語ったのは、あなた誰?というくらい、初めて見るクラスメイトでした。
意図的に、その知らないクラスメイトにその役を与えているのはわかるのですが、やっぱり初めて見る人が、しかも涙ながらに言っていることに対して、感情移入することは難しいと感じました。
また、三人組がボーリング場にいることを、先生は友人から連絡を受けます。
このため、先生が先に見つけるかと思いきや、そうではなかったという点も違和感を感じました。
お互いに知らない人同士で会話させることに重きを置いたことは理解できます。
ですが、感情移入の難しさや、そうした場面設定を作り出す過程の不自然さの意味でも、普通に先生に発見させて、そこでは多くを会話せず、教室に戻ってから話を展開してもよかったのではと思いました。
かなうって誰?
鵜久森叶(うぐもりかなう)の母親が教室に登場して、生徒に語りかけるシーンは感動的です。
一つだけ違和感があったのは、今までずっと鵜久森さんと呼ばれてきたのに、母親が言及するときには、叶(かなう)と下の名前で呼んでおり、かなう?って何?誰?となり、感情移入が少し妨げられるきらいがあったと思います。
そもそも、叶(かなう)という音を聞いても、下の名前だと認識しずらいです。
誰も安易に人を傷つけない世界が来てほしいという願いを実現するために動いていた鵜久森さんだからこそ、想いを込めてその名前にしていることはよくわかります。
この名前でいくなら、もう少し母親のセリフで、「娘の叶が」など、鵜久森さんの下の名前であることが馴染むまでは、単独で叶(かなう)を使うのはやめた方が良かったのではないかと思います。
突き落とした犯人について
犯人の設定は、視聴者の予想を裏切っていて、素晴らしいと思います。
犯人にスポットライトを当てた回はないですが、ところどころに登場させており、犯人であることが判明した時に、誰?とならなかったのはよかったと思います。
とは言え、今まで出た人で、取り上げられていない人を考えると、自ずと犯人として予想がついてしまうのが残念でした。
また、犯人の無気力、無関心な態度は、最後に明かされますが、そこを事前にもう少し描いても良かったのではないかと思います。
もちろん、描きすぎると、犯人であることが事前にわかってしまうので、さじ加減が難しいですが、動機に無気力、無関心を持ってきて共感を得るためにも、そこはもっと事前に描いてよかったのではないかと思います。
全体的にはうまくいっている
上に書いた違和感は、教師ものでは避けて通れないことが原因となって生じています。
それは、生徒が多いので、全員にスポットライトを当てて、詳しく解説している時間がないということです。
この作品は、そんな制約の中でも、例えば、一話で一人に焦点をあてるのではなく、二人がペアになっているエピソードにするなど、いろんな工夫で、より多くの生徒を取り上げることに成功していると思います。
ですので、全体的にはとても上手くできている作品だと思います。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
教師ものは飽きるほど見たという方、教師ものは説教臭くていやだという方、そんな方にこそ、見てほしいと思います。
言葉の力って、本当にすごいと、思わせてくれました。