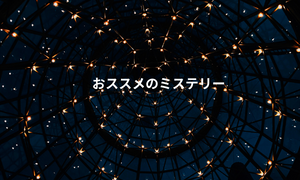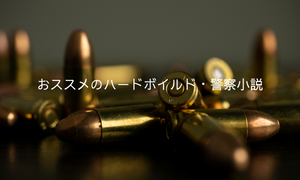『原発事故 最悪のシナリオ』石原大志
📁世の中のリアル 【私の評価】★★★★☆(89点)
2011年3月11日に発生した東日本大震災。
大きな津波が、福島第一原子力発電所を襲い、日本全体を不安・恐怖・混乱に陥れました。
日本は、一体どうなってしまうのだろう。
ニュースが報じる福島第一原発で生じた爆発と、真っ青な空に立ち昇る白い煙を見て、足元が崩れるような感覚を覚えました。
ニュースは、毎日、原発の状況を報道しますが、一向に状況は改善されず、むしろ悪化していました。
「格納容器」、「水素爆発」、「燃料棒」、「メルトダウン」。
テレビの解説者が次々に聞きなれない言葉を口にします。
不安な私たちは、テレビにかじりついて、今の状況を把握しようとしました。
福島だけでなく、首都圏でも高濃度の放射線が観測されたとの報道もありました。
下水など溜まっている場所は危ない。
放射線測定器を買い求める人が増えました。
そして、あれから12年が経ちました。
人々に深い不安と恐怖を与えた、未曽有の原発事故。
未だにその記憶を鮮明に覚えている方も多いと思います。
1986年4月のチェルノブイリ原子力発電事故以来、最も深刻な原子力事故となりました。
自己評価の深刻度のレベル7段階レベルのうち、福島の原発事故は、当初はレベル5に分類されていたようですが、のちに最高レベルの7(深刻な事故)に引き上げられています。
レベル7は、チェルノブイリと福島の原発事故の2つだけです。
あの時、一体、何が起こっていたのか。
そのことがずっと気になっていました。
そんな時、当時の吉田所長をはじめとした東電の職員の方々が、事故への対処を行うリアルな映像が公開されたと耳にしました。
You Tubeでもアップされています。
映像が公開された時、「どのみち、吹っ飛ぶ」などの東電側の発言が、ニュースでも取り上げられました。
映像を見ると、現場は大混乱で、本店と現地対策本部との切羽詰まったやりとりなど、当時は生きるか死ぬかの瀬戸際だったことが伝わってきました。
それから数年後、本書『原発事故 最悪のシナリオ』と出会いました。
本書は、2021年3月に放送されたNHK・ETV特集「原発事故『最悪のシナリオ』そのとき誰が命を懸けるのか」の取材をもとに、NHKディレクターである筆者が加筆した一冊となっています。
原発事故時の総理大臣の動きなど、事実や取材結果などが、丁寧に記載されています。
映像とはまた違って、あの原発事故とは何だったのかに迫る内容となっています。
本書の「最悪のシナリオ」とは、表紙にもありますが、東日本壊滅のことです。
そして本書は、原発事故への政府の対応を検証し、最悪を想定した迅速な対応などができていたのかという視点から、日本の危機管理に疑問を呈しています。
私が個人的に衝撃を受けたのは、実はその部分ではありませんでした。
私の記憶では、テレビに映った爆発が、最も危機的な瞬間だったと思っていました
爆発は二度ありました。一号機の爆発、それから三号機の爆発です。
ですが、本書を読んで、それは誤りだったと気づきました。
二号機の格納容器の破損の疑いの方が、かなり危機的だったようです。
そして、それ以上に、四号機の燃料プールの燃料露出の疑いが、最も危機的だったとわかりました。
燃料プールの燃料棒は、格納容器にも入っておらず、むき出しの状態です。
仮にプールの水がなくなっていたら、水をかけると大爆発して、核燃料が飛び散る恐れがあったようです。
考えただけでも恐ろしい状況です。
そのような危機的な状況の中、テレビでも報道されたので、覚えている方が多くいらっしゃると思いますが、自衛隊のヘリが上空から水をかけました。
そして、自衛隊が水をかけて爆発しないことを確認できたため、その後、水を地上からも注入できたようです。
結局、プールの水はなくなっていなかったことが、最大の幸運だったようです。
私たちが、あの原発事故後も、今、この日本で、暮らしていけていること、これは運がよかったとしかいいようがないことを、痛感させられました。
この本をおススメする理由は、原発再稼働について、考えてほしいということではありません。
原発について賛否を問いたいわけでも、私がどちらかの立場をとって、それを主張したいわけでもありません。
私が衝撃を受けたのは、あの原発事故の最も危機的な状況について、正確に理解していなかったことでした。
本書を読んで、それがわかったのです。
原発についてどのような立場をとるにしろ、あの福島第一原発の事故について、何が起き、どうやってくぐりぬけることができたのか、そこをまず知ることがとても大事だと思います。
紙一重。本当に紙一重だった。
そのことをしっかりと自覚することから、未来への歩みの第一歩が始まるのだと思います。