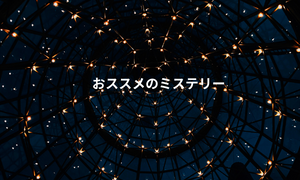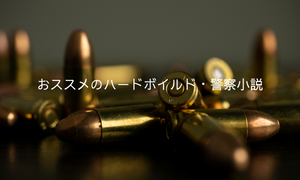九段理江さんの「東京都同情塔」を読みました。
この作品は、第170回芥川賞受賞作品です。
ネットのレビューを見ると、難解だったという感想が多く見られます。
確かに、難しい箇所もありました。
ですが、芥川賞受賞作の中では、比較的読みやすい作品なのではと感じました。
読んで見て感じた、魅力、感想などを書いていきたいと思います。
1.牧名沙羅(まきなさら)と「言葉」について
主人公の牧名沙羅(まきなさら)は、強烈な個性をもつ主人公です。
有名な建築家であるだけでなく、「言葉」に異常なほどの執着を持ちます。
主人公の頭の中には検閲者がいて、主人公が発した言葉や、発しようとする言葉を、それが適切な表現なのか、うるさいくらいに問い続けます。
この作品の随所に、こうした検閲者とのやりとりが出てきます。
そして、私は読んでいて、言葉の検閲ということに、新鮮さを感じました。
テレビ、インターネット、SNSなど、世界中の映像、文字、言葉が氾濫する世の中で、私たちは流れるように言葉を聞き、聞き流し、消費しています。
言葉について、それが合っているのか、間違っているのか、自分に問うということを無くして久しいことに気づかされます。
今の時代、言葉なんて、スマホやパソコンでカタカタと打って、伝わなければ削除したり、言葉をまたカタカタと重ねて打てばいいし、裏アカで何も考えずに悪口を書き込んでしまうことだってできます。
生成AIは、次から次に、言葉を連ねて機関銃のように吐き出してきます。
自分の手で文字を書いて、手紙にしたためて送ったり、もっと昔なら、墨を擦って筆にしみこませて、貴重な和紙に丁寧な字で書いていく、そういう時の言葉というのは、今とは違って、口に出したり書く前に、頭の中で検閲されていたもののはずです。
そして何より、自分の頭の中で検閲している時には、この言葉なら相手に伝わるだろうかと、相手のことをおもんばかる行為があったのだと思います。
この作品の冒頭に、「喋った先から言葉はすべて、他人には理解不能な独り言になる」「大独り言時代の到来」というセリフが出てきます。
言葉を容易に繰り出せるようになったからこそ、その言葉の重みがなくなり、相手を想う気持ちがなくなり、誰にも通じなくなって、単なる独り言になっている、そんなメッセージが強く伝わってきました。
そして、主人公は建築家です。
建築家にとって一番困るのは、建物が崩れてしまうことを一番恐れます。
だから主人公は、「強い意志と義務を示すコンクリートのように硬質な言葉」を好みます。
建築家と、検閲された強くて重い言葉が、よくマッチしていると思います。
さらに言えば、主人公は人間を、「思考する建築」「自立走行式の塔」とさえ見ています。
建築物である人間が、何も考えずに軽薄に出てくる言葉を使うことは、あるべきではないと主人公は思っているのだと思います。
2.生成AIについて
本作品では、主人公が生成AIに質問し、生成AIの返答を引用していると思われる部分が複数出てきます。
私もこの作品を読む前は、生成AIを活用して作られた作品だというおぼろげな知識をもったまま読みました。
ですが、この作品の主人公は、生成AIを「文盲」と言い放ちます。
生成AIに感心するのではなく、むしろ軽蔑しているのです。
生成AIを万能のように見なすのではなく、むしろ小馬鹿にしつつ活用している、そんなところが面白かったです。
3.塔について
この作品の冒頭から、主人公はシャワーを浴びながら、ずっと塔について考えています。
具体的には、塔の名称についてです。
「シンパシータワートウキョウ」という呼称が、主人公の頭に浮かび、こびりついて離れなくなります。
読者からすれば、これは一体、何の塔なのだろうと思うのですが、十数ページを読んで、やっと、それが「刑務塔」であることが判明します。
見事だなと思います。
読者の関心をずっと惹きつけておいて、結論が、受刑者を収容するための塔だとは、意外だからです。
その後、なぜそれをシンパシータワーと言うのか、明かされていきます。
ですが、主人公はカタカナが嫌いです。
主人公が、その言葉を、主人公の友人である拓人に尋ねると、拓人は日本語に置き換えて、「東京都同情塔」と言います。
主人公はそれを聞いて絶賛します。
特に、「東京同情塔」ではなく、「東京都同情塔」と言ったことに感銘を受けます。「都」をつけることで、音的にも適度な厳しさもあって、これで塔が崩れることはないと主人公は言います。
私も、「都」があるとないでは、全く違うなと感心しました。
「東京同情塔」は、「東京タワー」のように、どこか聞き慣れた響きがあります。
ですが、この本を手にとった時に、東京都同情塔という題名について、「都」があえてついていることに違和感を持ったのです。
なにかひっかかりを感じたので、そこがいいと思います。
ちなみに、興ざめなことを言ってしまうようですが、現実的には「東京都同情塔」という名称は成立しないと思います。
と言うのも、刑務所は国の施設であり、東京都を含む地方自治体の施設ではありません。
例えば、国税局は国の機関ですので、東京都国税局ではなく、東京国税局なのです。
刑務所も、府中刑務所、横浜刑務所など、都市の名前が付いていますが、国の機関ですので、都や市はつきません。
主人公は「都」が付くことで、この塔は崩れないほど固いものになったと感じたようですが、「都」がつくことで、架空の塔になってしまったというのが、私の感想です。
ですが、そんなことは些末な話です。
都があった方が名称として面白いことは確かだと思います。
4.社会学のような小説
最後に、この作品は、社会学のような側面も持っていると感じます。
罪を犯した人は、その人が悪いのではなく、その人が置かれた環境が悪かったせいだと考える。
罪を犯していない人は、その人の置かれた環境が恵まれていたせいで、犯罪を犯さなくてもよかった幸運に恵まれたからだと考える。
これは100%同意できるものではありませんが、一部は言い当てていると思います。
犯罪者を、同情されるべき人だと捉えて、罰を与えず、むしろ我々の税金により、我々以上に自由で恵まれた生活を与える。
そんな塔が私たちの目の前にできたら、私たちはそれを受け入れられるだろうか。
この作品は、犯罪者を同情されるべき人だと捉えるか否かを問うているのではなく、そうした避けられない問題を目の前に強固な塔のように打ち立てられた時、人はどういう言葉を用いて、どのように言葉を交わすのか(罵り合うのか、怒鳴り合うのか、独り言を言い合うのか、あるいは伝え合い、議論し、わかりあうのか)ということを、問うているのだと思います。
5.おわりに
私は、この作品の本質の半分も解説できていないかもしれません。
また、本来、作者の能力からすれば、もっと難解なものにもできたはずだとも思えます。
ですが、作者自身が読者のことをおもんばかり、伝えようとしてくれて、「言葉」、「検閲」、「建築」、「生成AI」などのキーワードを使って、解読にヒントを与えてくれているような気がしました。
丁寧に読めば、理解できる作品だと思います。
とってもおススメな作品です。